皆さんから寄せられた5万件以上の書評をランキング形式で表示しています。ネタバレは禁止
していません。ご注意を!
海外/国内ミステリ小説の投稿型書評サイト
ログイン
|
[ 冒険/スリラー/スパイ小説 ] ロシア・ハウス |
|||
|---|---|---|---|
| ジョン・ル・カレ | 出版月: 1990年04月 | 平均: 4.00点 | 書評数: 1件 |
 早川書房 1990年04月 |
 早川書房 1990年04月 |
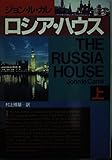 早川書房 1996年04月 |
 早川書房 1996年04月 |
| No.1 | 4点 | Tetchy | 2025/11/12 00:29 |
|---|---|---|---|
| ロシアではなくソ連と呼ばれていた時代の話で、舞台はゴルバチョフ書記長によって推し進められたペレストロイカの時代でイギリスの一介の出版社社主がソ連の出版社の編集者からもたらされた軍事兵器の漏洩情報に関係することで英米の諜報の世界に巻き込まれる物語である。
これまでガチガチの諜報の世界に住まう人々の息の詰まるような情報戦と人間性の狭間で足掻く人間ドラマを描いてきたル・カレが『リトル・ドラマー・ガール』以来、一般人が諜報戦に巻き込まれる物語を描いたのが本書だ。 ただ『リトル・ドラマー・ガール』ではスパイの訓練を受けた女優が工作員となるのに対し、本書のスコット・ブレア、通称バーリーは一介の出版社の社主に過ぎない。従って彼はスパイの訓練を受けるわけではなく、英国情報部の雇用者として彼らの諜報活動の協力者となる。つまり彼らの作戦にとって必要不可欠な人物として扱われるため、戦いの特殊訓練を受けるなどはないが、盗聴マイクや慎重な会話の仕方、相手から言質を取る話し方などを訓練させられる。バーリーの世話役として任命されるのが英国情報部のソ連担当部署ロシア・ハウスのチーフであるネッドだ。 このような一般人でありながら諜報活動に協力している、またはさせられている人たちのことを彼らはジョーと呼ぶ。また彼らのターゲットとしている相手国の重要機密を握る人物をブルーバードと呼ぶ。私もこれまでいくつかスパイ小説を読んできたがル・カレが使う俗称や略語は独特である。いや寧ろ彼の作品に盛り込まれている単語こそが実際英国情報部で使われているリアルな会話のように思える。 そしてソ連に渡ったバーリーことスコット・ブレアは当初はカーチャのことなど知らぬ存ぜずを通すが、一目逢うとその美しさに魅かれ、やがてお互い恋に落ちてしまうのだ。 つまりこれはル・カレ版『ロシアより愛をこめて』ではないだろうか。 そしてソ連にコネクションを持つイギリスの出版社アバークロンビー&ブレア社の社主バーリーとソ連の出版社オクトーバーの女性編集者カーチャことエカテリーナ・オルロヴァとの恋愛がいつしかソ連の科学者から持たされた軍事兵器情報を巡る米英の諜報合戦が等価値で語られていくようになる。 まずソ連の出版社から持たされたソ連の科学者によるソ連の軍事機密について書かれた暴露ノート。バーリーが出版を請われたそのノートにはソ連の軍事ミサイルの脆弱さが詳らかに書かれており、それはアメリカや英国にとっては非常に喜ばしい情報のはずなのだが、アメリカはソ連のハードウェアは精確無比であるとの確信の上に成り立っているため、逆にもたらされた情報を信じることができないというパラドックスに陥る。 従ってこれは米英を油断させるためにソ連が仕組んだものではないかと、ソ連の貴重な情報源を接触し、情報の持ち主であるバーリーは実はソ連側のスパイであるか否かについて、CIAから厳しい尋問を受ける。 しかし面白いのはそんな尋問をしている側もバーリーの人間的魅力を認め、彼に愛されたがっているのだ。 この実に奇妙な心理状態。即ち諜報活動とは決して論理的思考のみが突出したわけではなく、感情的な心理もまた同等に働き、人間である彼らもまたこの相反する情理の狭間で惑いながらやるべきことをしていることが判るのである。 ここで面白いのが英国情報部とCIAそれぞれの反応だ。 英国情報部はもはや我関せずを貫き、全く関与しようとせず、CIAはその存在すら、なかったことになっていたのだ。 つまり双方の考えは実に一致していた。“今更寝た子を起こすな”と。 ところで本当にしょうもないことなのだが、どうしても気になるのでここで述べておきたい。 妙に気になったのだが物語の発端となるカーチャからバーリーへの橋渡し役になる出版セールスマンの名前ニキ・ランダウはあのF1レーサー、ニキ・ラウダから採っているのだろうか? しかし英国人というのはどうしてロシア女性に惚れるのだろう。先ほど例に挙げた『ロシアより愛をこめて』の作者、007シリーズのイアン・フレミングといい、かのスパイ小説の雄であるブライアン・フリーマントルも自身のシリーズキャラ、チャーリー・マフィンもまたロシア人女性ナターリヤ・フェドーワと諜報戦の中で知り合い、運命の女性となって結婚までしてしまう。英国男性にとってロシア人女性というのは一種憧れの存在なのだろうか。 自身がその身を措いていたことでル・カレのスパイ小説は最もリアルに諜報の世界に生きる人々を描いた小説だと云われるが、彼の作品のカギを握るのはやはり女性である。男の世界と云われる諜報の世界だが、計算高いエリートたちが作り上げていく堅牢な知謀計略に綻びをもたらすのは女性の影があれば十分なのだ。 そう考えると最後の一行に添えられた、作中で何度も繰り返された教訓めいた一行、“スパイ活動とは待つことである”が意味するところは即ちカーチャを待つバーリーもまた短期間であったとはいえスパイだったという意味であると同時に、女を待つことをスパイ活動に準えていることを考えれば、即ちスパイ活動とは女を待つことであるという意味なのかもしれない。 世界の情報戦は実は女性が陰で動かしているのかもしれない。 ル・カレの作品を読むとそんな風に思えてならない。 |
|||
キーワードから探す
ジョン・ル・カレ
- 2021年12月
- シルバービュー荘にて
- 平均:6.00 / 書評数:1
- 2020年07月
- スパイはいまも謀略の地に
- 2017年11月
- スパイたちの遺産
- 平均:4.00 / 書評数:2
- 2017年03月
- 地下道の鳩
- 平均:6.00 / 書評数:1
- 2014年11月
- 繊細な真実
- 平均:6.00 / 書評数:1
- 2013年12月
- 誰よりも狙われた男
- 平均:4.00 / 書評数:1
- 2012年11月
- われらが背きし者
- 2011年12月
- ミッション・ソング
- 2008年11月
- サラマンダーは炎のなかに
- 2003年12月
- ナイロビの蜂
- 平均:5.00 / 書評数:1
- 2000年12月
- シングル&シングル
- 1999年10月
- パナマの仕立屋
- 1996年05月
- われらのゲーム
- 平均:6.00 / 書評数:1
- 1994年07月
- ナイト・マネジャー
- 平均:6.00 / 書評数:1
- 1991年12月
- 影の巡礼者
- 平均:6.50 / 書評数:2
- 1990年04月
- ロシア・ハウス
- 平均:4.00 / 書評数:1
- 1987年04月
- パーフェクト・スパイ
- 平均:3.00 / 書評数:1
- 1983年11月
- リトル・ドラマー・ガール
- 平均:8.00 / 書評数:2
- 1981年05月
- スマイリーと仲間たち
- 平均:8.67 / 書評数:3
- 1979年07月
- スクールボーイ閣下
- 平均:7.00 / 書評数:4
- 1975年01月
- ティンカー、テイラー、ソルジャー、スパイ
- 平均:7.33 / 書評数:3
- 1974年01月
- ドイツの小さな町
- 平均:6.00 / 書評数:1
- 1966年01月
- 高貴なる殺人
- 平均:6.67 / 書評数:3
- 1965年12月
- 鏡の国の戦争
- 平均:6.33 / 書評数:3
- 1965年01月
- 死者にかかってきた電話
- 平均:5.00 / 書評数:3
- 1964年01月
- 寒い国から帰ってきたスパイ
- 平均:7.60 / 書評数:10
